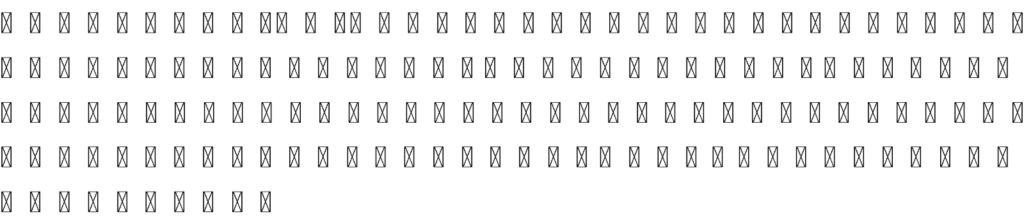創世記18章16~33節 2026年2月15日(日)主日礼拝説教
牧師 藤田浩喜
今日の聖書は、アブラハムに神の使いが現れたということが書かれている箇所です。そしてこの神の使いは、アブラハムにこういうふうに言いました。17~18節です。「主は言われた。『わたしが行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る』」。
ここで、アブラハムという人物、一人の人間に神の祝福があらためて約束されます。アブラハムとその子孫が祝福を受けるという約束です。アブラハムとその子孫は大いなる国民となって、強い国民となって、人々の中に住むと言われています。しかしそれは、アブラハムとその子孫たちだけが祝福されるという意味ではありません。こう言われていました。「アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る」と。世界のすべての国民は、このアブラハムとその子孫の存在によって祝福に入れられるというのです。
祝福に入るというのは、祝福の輪の中に引き入れられるということです。アブラハムとその子孫が神の祝福の中で生きることによって、周りの人々も、その祝福の中に引き入れられると言われているのです。ですから、アブラハムの祝福というのは、彼とその子孫だけが祝福されるということではありません。神の祝福の世界に生きる、そのことによって他の人々が祝福に入れられるというのです。
信仰というのは、言うまでもなく神を知ることです。神が存在しておられることを知ること。しかし、神様がどこかにおられることを知ることだけが信仰ではありません。自分の存在が、この自分の命が祝福されているということを知ること、それが信仰です。この命が、この自分の命が神に喜ばれている、それを知ることが私たちの信仰です。そしてそのことを本当に知る人は、その喜びを他に伝えようとするのです。つまり、自分のこの命が祝福されているというその喜びを、他の人に伝えないではいられないのです。
こんなたとえが許されるかもしれません。打ち沈んでいる人々の中に一人の喜んでいる人間がいる。そのことによって、この集団全体が支えられるということがありうるのです。あるいは、みんなが希望を失っている中に、少数の希望を失わない人間がいることによって、その全体が支えられるということが起こりうるのです。それが、信仰者がこの世に生かされていることの意味だということを知りたいと思うのです。
沈みかけている船から、みんなが逃げ出そうとしている時に、その船の中に踏みとどまっている人間がいることによって全体が支えられる。イエス・キリストは弟子たちに、あなたがたは地の塩であると言われました。少数の、少量の塩が物の腐敗を防ぎます。少量の塩が料理全体の味を引き立てます。少数の信仰者がこの世に遣わされていることの意味は、そこにあると思います。周りを支えるものとしてそこに遣わされているのです。
私たちはこの世の人々のことを嘆いたり、あるいは批判をしたりするためではない、そこで祈るものとしてこの世に遣わされているということを忘れてはなりません。私たちは自分の置かれている場所で、祈って支えるのです。それが信仰者のこの世における在り方です。アブラハムもそういう人間でした。
ここに、ソドムとゴモラの街のことが出てきます。ソドムとゴモラの街には罪が満ちて、人々の訴えが神のもとに届いていると書かれています。20~21節。「主は言われた。『ソドムとゴモラの罪は非常に重い、と訴える叫びが実に大きい。わたしは降って行き、彼らの行跡(ぎょうせき)が、果たして、わたしに届いた叫びのとおりかどうか見て確かめよう』」。
ソドムとゴモラの街から訴えが神のもとに届いたと言われています。この「訴え」という言葉は、ある註解書では「悲鳴」という言葉で言い換えていました。「悲鳴」、悲鳴が神のもとに届いた。
神の使いはソドムに向かいました。22~23節にこう書いてあります。「その人たちは、更にソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお、主の御前にいた。アブラハムは進み出て言った」。
神の使いはソドムに向かいました。これはもちろん、神の裁きを行うためです。
しかし、アブラハムはなお主の御前にいたと記されています。アブラハムは今まさに神がなそうとしておられることに、納得ができなかったからです。だから彼はなお主の御前にいた、と書かれています。
祈るということはそういうことでしょう。神の御心だからといって、何でも受け入れて引き下がるのは信仰ではありません。それは単なるあきらめです。信仰者というのは、祈る人間のことを指しています。踏みとどまって祈る。そして祈って神様の御心を知るのです。祈らないで、ああ神様の御心だから仕方がない、というのは全然神様の御心をわかっていないのです。祈って初めて私たちは神様の御心を自分に受けとめることができるのです。
アブラハムは神に、進み出て言います。「『まことにあなたは、正しい者を悪い者と一緒に滅ぼされるのですか。あの町に正しい者が五十人いるとしても、それでも滅ぼし、その五十人の正しい者のために、町をお赦しにはならないのですか。正しい者を悪い者と一緒に殺し、正しい者を悪い者と同じ目に遭わせるようなことを、あなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は、正義を行われるべきではありませんか』」(23~25節)。「主は言われた。『もしソドムの町に正しい者が五十人いるならば、その者たちのために、町全部を赦そう』」。(26節)。
アブラハムは祈るのです。まさに神が、神の使いがソドムに向かっている時に、神の前に踏みとどまって祈ります。一体神様あなたは、正しいものも悪いものも一緒に滅ぼされるのですか。五十人の正しい人があの街にいたならば、その五十人の人もソドムの罪と一緒に滅ぼされるのですか、と彼は神に問うのです。すると神は、いや五十人の正しい人がいたならば、わたしは滅ぼさないだろうと言われます。さらにアブラハムは五十人に五人欠けたらどうでしょうか、と聞きます。いや四十五人でもわたしは滅ぼさない。いや、四十人だったらどうでしょうか。いや三十人だったらどうでしょうか。いや三十人いたら、正しい人が三十人いたらわたしは滅ぼさないと神は言われます。二十人ではどうですか。そして最後に十人ではどうですか、とアブラハムは神に問います。十人の正しい人がいたらその十人のために滅ぼさないと、神は約束されます。
ここでアブラハムは、ただ祈っているのではありません。勇気を振り絞って、彼は迫っているのです。23節に「アブラハムは進み出て言った」と、神の前に進み出て言ったと言われています。それから27節では、「塵あくたにすぎないわたしですが、あえて、わが主に申し上げます」というふうに彼は神に祈っています。塵あくたに過ぎない自分ですが。そうやって数を減らしながら彼は勇気を絞って神様に祈り続けています。身を削るようにして彼は祈っています。神と向き合うということは、楽なことではありません。
私たちは、祈るということについてよく知っています。そんなに楽ではない。つまり、それが誰かとおしゃべりするようなことであるならば、もっと簡単に私たちには祈ることができるでしょう。しかし、そうではない。ちょうど波が岩にぶつかるように、ぶつかって砕けるように、人は神に向き合いながら変えられていくのです。自分が打たれる経験をする。神に祈りながら自分が砕かれる経験をする。そうやって自分が変えられながら、神様の御心がわかってくるのです。アブラハムは祈りながら、神の御心がわかってきました。それは、この世の人々を惜しむ神様の御心です。この世の人々を愛おしむ神の御心、それが祈りの中で、祈りながら彼にはわかってきたのです。
27節「塵あくたにすぎないわたしですが、あえて、わが主に申し上げます」、とアブラハムは言います。彼は塵あくたに過ぎない自分だということを自覚しています。神の御前に立つとそのことはよくわかります。自分は神様に何かを頼む、祈る資格なんかはある人間だとは思わない。しかし彼は祈るのです。なぜならば、赦されていることを知っているからです。自分は赦されている人間だということを知っているから、祝福されている人間だということを知っているから、彼は敢えて祈るのです。つまらない人間が、受け入れられていることを知っているから、だから彼は祈るのです。この塵あくたに過ぎない者の祈りを聞くために、神は私たちを救い出してくださっているのです。この私たちの祈りを聞くことを神様は望んでいてくださる。そのために私たちは救い出されているのです。
五十人いたら、という祈りから、もし十人しかいなかったらという祈りに変わります。それでもこの街全体を救っていただけますか。そして彼は十人のために滅ぼさないという神の答えを引き出します。そして、それ以上は聞きませんでした。一人ならどうですかということを聞くこともできたでしょう。しかしアブラハムは、それ以上は聞きませんでした。なぜなら彼は理解したのです。一人の正しい人がいたら、神はこの街を滅ぼされないのだということを。一人の正しい人のゆえに街全体は滅ぼされないのだ、ということを彼は理解しました。だから彼は、これ以上は祈らなかったのです。
私たちは救い主イエス・キリストの十字架上の祈りを思い出します。ルカによる福音書23章34節の祈りです。「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」。十字架の周りには、このキリストを十字架につけた人間たちが騒いでいます。罵っています。自分たちの傲慢と思い上がりによって、罪なきものを十字架に抹殺しようとしている人間たちが、十字架の周りにひしめいています。そしてもしこの群衆を滅ぼしてしまえば、この傲慢な思い上がった人間を滅ぼしてしまえば、それで問題は解決するのです。つまり、罪人は滅ぼしてしまえば、これで問題は解決するのです。
しかし神は、そのように問題を解決しようとはなさいませんでした。ここにイエス・キリストの一つの祈りがあるのです。「父よ、彼らをお赦しください。彼らは何をしているのか知らないのです」。人々の罪ゆえの呪いを神から一身に受けながら、イエス・キリストは十字架の上でそのように祈られました。
この祈りによって私たちは救われています。この祈りによってこの世は守られています。私たちのうちの誰か、どこかに正しい人がいるのではないのです。義人はいない。一人もいない。誰もいません。しかしこの世界には正しい一人がいるのです。十字架のイエス・キリスト。だからこの世界は捨てられません。この世界は滅ぼされません。この世界は呪われません。だから私たちも呪われてはいない、呪われない、そのことを私たちは知っています。
このキリストの祈りを知っている私たち、私たちもこの世の只中で祈るのです。この世のために私たちも祈る、自分の周りにいる人々のために私たちも執り成しの祈りをするのです。なぜならそれが神の国の業だからです。そうやって私たちは神の国の業に、この罪人が参与していくのです。
多くの人々はこの世にあって、この世を嘆き、この世を恨み、この世の人々を批判する。しかし、私たちはこの世の只中にあって、あのイエス・キリストがしてくださったように、いや、今もこの世がイエス・キリストの祈りによって支えられていることを知っているから、私たちも遣わされた場所で祈る人間になるのです。執り成しの祈りをする人間になるのです。
それが、神の民としてこの世に遣わされている私たちの存在の意味だということを忘れてはなりません。お祈りをいたしましょう。
【祈り】主イエス・キリストの父なる神さま、あなたの貴き御名を讃美いたします。今日も敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。アブラハムの祈りを通して、私たちがひとりのお方イエス・キリストの祈りゆえに救われていることを知りました。どうか、主に倣って私たちも、世のために執り成しの祈りを捧げ続けていくことができるようにしてください。群れの中には、病気の兄弟姉妹、高齢のため困難を抱えている兄弟姉妹がおります。どうか、神さまが兄弟姉妹と共にあって、一人一人に励ましと平安を与えていてください。このひと言の切なるお祈りを、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。