日曜学校
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 創世記6章9~22節
説 教 「箱舟」 藤田浩喜牧師
主日礼拝
午前10時30分 司式 三宅恵子長老
聖 書
(旧約) 列王記上3章9~13節
(新約) ヤコブの手紙1章1~8節 (Ⅰ)
説 教 「試練に出会うときは」 藤田浩喜牧師
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 創世記6章9~22節
説 教 「箱舟」 藤田浩喜牧師
午前10時30分 司式 三宅恵子長老
聖 書
(旧約) 列王記上3章9~13節
(新約) ヤコブの手紙1章1~8節 (Ⅰ)
説 教 「試練に出会うときは」 藤田浩喜牧師
マルコによる福音書15章21~32節 2026年1月25日(日)主日礼拝説教
牧師 藤田浩喜
主イエスは、十字架の苦しみをお受けになりました。それは文字通りの死に至る苦しみでした。しかも、まことの神の御子でありながら、人々に罵(ののし)られ、辱められるというものでした。この十字架に架けられたお方を、私たちは我が主、我が神と信じ、今朝も礼拝しています。この主の十字架こそ私たちの救いの根拠であり、神様の愛と真実が現れたものだからです。
今朝与えられております御言葉において、主イエスが十字架に架けられた時、兵士たちは主イエスの服をくじ引きにして分け合い、主イエスの十字架を見た人々は主イエスを罵り、辱めて、こう言ったと記されています。「おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。」「他人は救ったのに、自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう。」このように、主イエスは十字架に架けられても尚、罵られ、辱められたのです。何ということかと思います。
しかし、先ほど読んでいただきました詩編22編には、すでにこの情景が預言されていました。22編8~9節「わたしを見る人は皆、わたしを嘲笑い、唇を突き出し、頭を振る。『主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。』」そして、18~19節「骨が数えられる程になったわたしのからだを彼らはさらしものにして眺め、わたしの着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く」とあります。これは明らかに今朝与えられている主イエスの十字架の場面と重なります。この詩編の言葉は、主イエスが十字架の上で人々に罵られ、辱められたこと。そして主イエスの服が兵士たちによってくじ引きされて分けられたという、今朝の御言葉が告げる主イエスの十字架の場面と全く重なるわけです。このことは、主イエスの十字架の出来事が、神様の永遠の御計画の中にあったことを意味しているのでしょう。主イエスが十字架の上で、人々に罵られ辱められることを、神様は御存知であったということです。そして、それは主イエスも承知の上であったということでしょう。では、なぜ主イエスはこれほどまで人々に辱められ、罵られなければならなかったのでしょうか。ここには、主イエスの十字架の意味が隠されているのです。
主イエスの十字架での苦しみの意味、それは、どんな状況の中に生きる人に対しても、「わたしはあなたを知っている。あなたの苦しみも困難も知っている。わたしはあなたと共にいる。わたしはあなたを見捨てない。あなたの苦しみ、嘆きをわたしは共に負っている。だから大丈夫。」そのように主イエスは語りかけ、苦しみのただ中にある者と共に歩む神であられるからです。それゆえ、主イエスは十字架の上で、肉体的にも精神的にも、人間が味わう極限の苦しみを味わわれたのです。
私たちは肉体的な痛みに弱いです。虫歯ができただけでも、情けないほどに弱ってしまいます。しかし、主イエスがここで受けている肉体の痛みは、死ぬまで続く痛みです。死に至る痛みなのです。手と足に釘を刺され、十字架に磔(はりつけ)にされる。傷口から血が流れ出て、出血多量のショック死に至る。午前9時に十字架に架けられてから、午後の3時に息を引き取るまで続く痛みです。23節には「没薬を混ぜたぶどう酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった」とあります。「没薬を混ぜたぶどう酒」というのは、痛みを和らげるための麻酔薬と思ってよいです。主イエスは、それを受けることを拒まれたのです。それは、十字架での痛み、死にいたる苦しみを味わい尽くすためでした。
また、私たちは人から辱めを受けることがあれば、もう生きていけないと思うほどに心が萎えてしまいます。あるいは、人に罵られれば、一生忘れることができない悔しさを心に秘めることにもなるでしょう。主イエスはここで、私たちが味わう肉体的痛み、心の痛み、そのすべてを極限まで味わい尽くされたのです。ヘブライ人への手紙4章15節。「この大祭司は、わたしたちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです」と告げている通りです。私たちの痛みも嘆きも、主イエスは御存知なのです。そして、私たちの痛みも嘆きも、御自分のものとしてくださるのです。そのことによって、主イエスは私たちの痛みと嘆きの向こうにある明日、さらに死の向こうにある復活の命へと私たちの目を向けさせ、私たちをそこへと招いてくださるのです。
主イエスは、一人で十字架の上で死なれたのではありません。主イエスの右と左には、同じように十字架に架けられた者がおりました。彼らは強盗であったと聖書は記します。十字架に架けられて処刑されても仕方のない犯罪者でした。主イエスはその強盗と一緒に十字架に架けられたのです。それはまさに、死に至るまで罪人と共に歩まれる、神の御子の姿です。主イエスは、天地が造られる前から、天地を造られた父なる神と共に天におられました。しかし、そこから降って来て、馬小屋に生まれ、罪人と共に食事をし、病人を癒やし、そして最後は犯罪人と一緒に処刑されたのです。どこまでも罪人と共に歩まれる神の御子、どこまでも低きに降る神の御子の姿がここにあります。
私たちの中には、少しでも人より上に行こうとする思いがあります。しかし、主イエスはどこまでも低きに降ろうとされます。その極みが十字架だったのです。それは、どこまでも弱い者、小さい者、罪の中にある者と共にあり、誰一人としてお見捨てにならないお方だからです。だから、私たちはこの方を信じてよいのです。自分にとって得になる人にはよくしてやる。それが私たちにとっては普通でしょう。しかし、それは愛ではありません。主イエスによって示された愛ではないのです。主イエスはこの十字架において、まことの愛とはどういうものであるかを示してくださったのです。
主イエスが受けた罵(ののし)りは、「十字架から降りて自分を救ってみろ」、「今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう」というものでした。もし、主イエスがこの時十字架から降りたなら、私たちを救うために来られなされた歩みが、すべて無駄になってしまいます。それだけではありません、天地創造以来の神様の永遠の御計画が無に帰してしまうのです。そして、誰一人救われる者がいなくなってしまうわけです。ですから、主イエスは十字架からお降りになりませんでした。
しかし、この時ほど、主イエスとサタンとが激しく戦われた時はなかったのではないかと思います。この主イエスを罵る人々の背後にはサタンが働いている、そう言ってよいでしょう。サタンは、神様の救いの御計画、主イエスの十字架によって成就する救いの御業を失敗させるために、最後の最も激しい誘惑、霊的戦いを主イエスに仕掛けていたのだと思います。もし、主イエスがこの辱めに耐えかねて、「我こそはメシア、神の独り子、イスラエルの王である」と言って十字架から降りてしまえば、サタンの勝利でありました。しかし、主イエスはこの最大の誘惑を退けられ、十字架の上で痛みと苦しみを味わい尽くされたのです。それは私たちの救いのためでした。それは私たちへの愛のゆえでした。この主イエスが、私たちと共にいてくださるのです。私たちのために、私たちに代わって戦ってくださるのです。
聖霊なる神様は、私たちに主イエスの十字架の御姿をはっきりとお示しになり、その愛の確かさ、救いの決意を教えてくださいます。この十字架の前で、私たちは目覚めさせていただくのです。自分の罪、自分の傲慢、自分の愚かさ、自分の怠惰、自分の思い違い、それをはっきりと知らされ、神様の御前に悔い改めるのです。主イエスのもとに、神様のもとに立ち帰るというのは、この悔い改めを必要とします。この悔い改めは、主イエスの十字架のもとで、十字架の主イエスとの出会いの中で起きることなのです。主イエスは御自分を救わず、私たちを救ってくださった。十字架から降りず、すべての痛みを味わい尽くされた。私のためにです。そのことを知ったとき、私たちは正直になれる。素直になれる。神様の御前に自らの罪を認める。そして「お赦しください、憐れんでください」と祈ることができるのです。
私たちにとって、体の痛みは本当に辛いものです。しかし、その痛みの中でこそ、十字架の主イエスが共におられるのです。そして、私たちに語りかけてくださる。「わたしはあなたの痛みを知っている。あなたはひとりではない。ほら、わたしが共にいる。わたしはあなたをひとりにしない。」また、人に罵られ、辱められ、心が萎え、生きる気力も失いかけた時、頭に血が上り、怒りに支配されそうになった時、十字架の主イエスが私たちに語られるのです。「わたしはあなたの怒りを、嘆きを、悲しみを、苦しみを、知っている。わたしも十字架の上でひとりだった。皆がわたしを罵り、嘲った。弟子たちも皆、わたしを捨てて逃げた。だから、わたしは知っている。だから、怒りに身を任せてはいけない。悲しみに支配されてはいけない。わたしが共にいる。わたしはあなたのために明日を備えている。それは十字架の死の後の、復活という明日だ。この悲しみの中でこそ、嘆きの中でこそ、あなたは十字架のわたしと一つになっている。だから、大丈夫。わたしは主。あなたを贖うために十字架に架かった者。」この御声を私たちが聞くなら、私たちは立ち直ることができるのです。
主イエスの十字架の罪状書きには、「ユダヤ人の王」と書かれていました。これは、主イエスがユダヤ人の王と称した、ユダヤを支配しているローマに反逆した者という意味で付けられたものでした。しかし、そこにはただ「ユダヤ人の王」とだけ書かれていたのです。「ユダヤ人の王と称した者」とか「ユダヤ人の王としてローマに反逆した者」とは書かれていなかった。ただ「ユダヤ人の王」です。
ユダヤ人の王。神の民であるユダヤの本当の王は、神様しかおられません。これは旧約以来の、神の民の基本的な理解です。この罪状書きは図らずも、主イエスがまことの神であられることを示す表札の役割を果たすことになってしまったのです。まことの神であられるユダヤ人の王は、この十字架に架けられた主イエスである。そのことを示すことになったのです。その意味では、この十字架がユダヤ人の王、まことの神としての主イエスの即位式となったのです。
私たちはこのまことの王である主イエスのもの、主イエスに属する者とされたのです。クリスチャン、キリスト者とは、キリストのものとされた者ということです。私たちは、この十字架にお架かりになった主イエスのものなのです。主イエスの御支配のもとに生かされており、主イエスの復活の命に与る者とされているのです。ですから私たちは最早、自分のために生きるのではないのです。私たちの人生は、ただ一人の主であり王である主イエスのものだからです。このお方と共に、このお方のために生きる。そこに私たちの喜び、希望、誇りがあるのです。この恵みに感謝し、ご一緒に主をほめたたえましょう。お祈りをいたします。
【祈り】主イエス・キリストの父なる神さま、あなたの御名を心から褒め称えます。今日も愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。神さま、あなたは御子イエス・キリストを私たちの世界に遣わされました。主イエスは十字架に架けられ、すべての肉体的痛みと精神的な苦しみを経験されました。そのことを通して、主イエスは「あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われ」ましたが、それは主イエスが徹頭徹尾、弱い私たちと共に歩んでくださるためでした。どうか、そのことを決して忘れることがありませんよう、わたしたちの心に刻ませてください。今日は午後に年に一度の教会総会を行います。この教会会議を通して、過ぎし一年のあなたの恵みの感謝し、新しい一年の伝道のビジョンを与えられますよう、この教会総会を終始導いていてください。この拙き切なるお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 創世記4章1~16節
説 教 「カインとアベル」 三宅光
午前10時30分 司式 髙谷史朗長老
聖 書(旧約) イザヤ書60章1~7節 (聖餐式を執行します)
(新約) フィリピの信徒への手紙4章10~23節
説 教 「神に栄光」 山田矩子教師
マルコによる福音書15章16~21節 2026年1月18日(日)主日礼拝説教
牧師 藤田浩喜
主イエスは、ピラトによって十字架に架けられることとされ、鞭で打たれて兵士たちに引き渡されました。この鞭打ちは、それだけで息絶えてしまう者がいるほど激しいものでした。革の鞭に鉄や石の鋲(びょう)が付いているもので打たれるのです。背中からもお腹からも血が流れたことでしょう。主イエスは、もう立っていることができないほどに痛めつけられました。
その弱り果てた主イエスを、さらにローマの兵士たちがなぶりものにしたのです。まず主イエスに紫の服を着せます。これは多分、ローマの兵士たちが着ていた赤紫の短いコートのようなものだったと思います。それを、王様や皇帝が着る紫のローブに見立てたのです。そして、王冠の代わりに茨の冠を編んでかぶらせました。茨には5cmほどの硬いトゲがあり、そのトゲが主イエスの頭や額に突き刺さり、血が流れたことでしょう。
死刑になることが決まっているのだから、どんなに痛めつけても同じこと。兵士たちは、日頃の憂さ晴らしのつもりだったのでしょうか。人間の奥底には、日頃は表に出ることはあまりありませんが、人を痛めつけ苦しめることに喜びを覚えるという闇があるのでしょう。その人が一番嫌なこと、苦しいことを見つけて、そこを突いてくる。しかし、主イエスはこの時も黙っておられました。主イエスは嵐を静めることもできたし、病の人々を癒やすこともおできになりました。その力を、主イエスはこの時、御自分のためにお使いにはならなかったのです。
兵士たちは、主イエスの前にひざまずき、主イエスを拝む仕草をして、「ユダヤ人の王、万歳」と言ってはやし立てたのです。鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、体中傷だらけになったその体に、安っぽい赤紫の服を着せられ、偽りの礼拝を受け、「ユダヤ人の王」と言ってはやし立てられる。主イエスはまた、王様の持つ笏(しゃく)を模した葦の棒を持たされました。そして、その棒で頭を叩かれ、唾を吐きかけられ、「ユダヤ人の王」とはやし立てられました。神様が最も嫌われる、偽りの礼拝。神様を侮る行為。「もう赦せない。勘弁できない。」そう言って立ち上がってもよさそうなものです。しかし、そこまでされても、主イエスは神の子としての力をお使いにならず、ただ兵士たちがするままにされました。
こんな神様がいるでしょうか。鞭打たれ、足元もおぼつかないほどに弱り果て、兵士たちに侮辱され、それでも何もしない。ただただ痛めつけられている神です。主イエスは、十字架を背負わされ、ゴルゴタという所まで歩かされます。主イエスの周りには、主イエスをはやし立てる群衆がいたことでしょう。主イエスは黙って、十字架を背負って歩まれました。
主イエスが歩まれた道は、「悲しみの道」と呼ばれます。これはラテン語で「ヴィア・ドロローサ」と言い、主イエスが裁かれたピラトの官邸から、十字架に架けられ、死んで葬られた墓までの道、エルサレムにある1kmほどの小道につけられた名前です。今も毎週金曜日には、カトリック教会のフランシスコ会の主催で、十字架を担いだ修道僧の後を付いて多くの人々がその道を歩みます。その道には14のステーション、とどまる所があって、主イエスがここで鞭打たれた、から始まり、ここで十字架の重さに膝を折られた、ここで十字架に架けられた、と続くわけです。その14のステーションで、主イエスの御姿を思い起こし、祈るのです。主イエスのこの十字架への歩みを思い起こして祈る。主イエスの十字架へと歩む姿を心に刻むようにして祈る。
これは、エルサレムのヴィア・ドロローサにおいてだけ行われているものではないのです。これは「十字架の道行き」と言って、四旬節、レントの期間には必ず、金曜日にカトリック教会で行われるものなのです。そのために、カトリック教会の礼拝堂には必ず、壁に14のステーションを示す絵なり、レリーフなりが飾ってあるのです。広い敷地を持つ修道院では、山や庭にこの14のステーションが作られている所もあります。私たちには、「十字架の道行き」を行うという伝統はありません。しかし、イースターの前、受難節・レントの期間に、主イエスの苦しみを心に刻むということは同じです。やり方は違いますが、主イエスの苦しみを心に刻むということにおいては、変わることはありません。
しかし、どうして代々のキリスト者たちは、この主イエスの苦しみ、御受難を心に刻んできたのでしょうか。理由は、二つあると思います。
第一に、この主イエスの苦しみは私のためである、ということを心に刻むためです。主イエスは、これほどの苦しみを私のために、私に代わって受けてくださったということ。ここに、主イエスの私たちへの愛がはっきりと示されているからです。こんなにしてまで、私を救おうとしてくださった主イエス。その主イエスの苦しみの姿を心に刻み、主イエスの愛を思うのです。愛は、愛するその人のために苦しむことをも引き受けることです。主イエスの苦しみは、その私たちへの愛の極みなのです。主イエスはこの時、この苦しみから逃れようとすればできたのです。でも、そうはされなかった。自分を助ければ、私たちを救うことができないからです。私たちの身代わりにならないからです。
第二に、私たちが主イエスの苦しみの姿を心に刻むのは、私の苦しみが主イエスの苦しみにつながっていることを心に刻むためです。私たちはいろいろな苦しみを経験します。人に馬鹿にされたり、軽んじられたりすれば、夜も眠れないほどに腹を立てます。愛する者との関係が破れて、生きる意欲を失ってしまいそうになることもある。生活の苦しみもある。そのすべての苦しみが、この主イエスの苦しみとつながっている。主イエスは、苦しみの中にある人と共にいてくださるのです。苦しむ私と共に苦しんでくださっている。インマヌエルの神、我らと共にいてくださる神は、苦しみのただ中で、私と共にいてくださるのです。主イエスは、苦しみの中にいる者を決して一人にはしないのです。ヴィア・ドロローサ、悲しみの道を歩まれた主イエスは、私たちの悲しみを知っておられる、その悲しみの中で私たちと共に歩んでくださるのです。
私たちは苦しみの中で、ひとりぼっちのような気がするものです。誰も私の苦しみなんて分かってくれない。確かに、人は人の苦しみを分かることはできないでしょう。しかし、神様は違う、主イエスは違うのです。主イエスは知っている。知っているだけではなくて、私と共にいて、私と共に歩み、私を背負い、支えてくださる。私たちは苦しみ悲しみに出会いたくない。しかし、その苦しみ悲しみの中で、私たちは神と出会う、主イエスと出会うのです。
主イエスは刑場であるゴルゴタという所に着くまでに、もう十字架を背負うことができないほどに弱られました。十字架といっても、主イエスがここで担がされたのは十字架の横木ではなかったかと考えられています。この時、キレネ人のシモンという人が、たまたま通りかかります。そして、ローマの兵士はこの人に主イエスの十字架を背負わせたのです。彼にしてみれば、何のことやら分からず、何と運が悪いのかと思ったことでしょう。しかし、このことがこの人の人生を変えてしまいました。
21節に、この人は「アレキサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人」であったと記されています。どうして、この人の名が記されているのか。また、どうしてこの人の二人の息子の名前までもが記されているのか。このマルコによる福音書が記されたのは、主イエスが十字架にお架かりになってから30年ほど後のことです。ここで、名前が記されているということは、この福音書が記された時に、この二人の息子はキリストの教会ですでに名前を知られている人であったということを意味していると考えられます。つまり、主イエスの十字架を無理矢理担がされた人の息子はキリスト者になった。そして多分、シモンもキリスト者になったということなのだと思います。
どうして、何があって、そういうことになったのかは分かりません。しかし、長い教会の歴史の中で、このキレネ人シモンという人の有り様が私と同じだと、受け止める多くの人を生んできたのも事実なのです。何も分からずに、主イエスの愛の業に用いられることになってしまう。そうして、その業に仕えている中で信仰を与えられる。そういうことがあるのでしょう。私もそういう人に何人も出会ってきました。例えば、何も知らずに教会の幼稚園で働くようになり、そこで主イエスに出会って信仰を与えられた人などは、その典型的な例でしょう。キリスト教音楽との出会いの中で与えられた人もいるでしょう。神様は信仰のある人だけをその愛の業に用いるのではありません。自由に選んで用いられる、その営みの中で信仰が与えられるということは、決して少なくないのです。
そしてまた、このキレネ人シモンの姿は、キリスト教会の姿を指し示すものとして受け止められてきました。つまり、主イエスの十字架を背負って歩む教会ということです。主イエスの十字架を背負う。もちろん、罪の赦しを与える主イエスの十字架は、主イエスだけのものです。しかし、主イエスの救いを宣べ伝えるための労苦は、キリスト教会に与えられた務めです。それはこの主イエスの十字架を背負うということなのです。この主イエスの救いを宣べ伝える労苦というものは、主イエスの愛に仕えるということですから、具体的なあの人のために、この人のために喜んで労苦するということになるでしょう。私たちは、自分の労苦だけで精一杯と思っているかもしれません。しかし、私たちはそこから一歩踏み出していく者として召されているのです。
そうは言われても、私はもう年をとりました、人のためにもう何もできそうもありません。そう思う方もおられるかもしれません。もちろん、若くて元気な人は、それに見合ったことをすればよいのですが、年老いた者は何もできない。そんなことはないのです。なぜなら、私たちは「祈れる」からです。どんなに年老いても、体が動かなくなっても、私たちはその人のために、その人に代わって祈ることができるのです。それは、紛れもなく主イエスの十字架を担う行為なのです。世の人は主イエスを知りません。ですから祈ることも知りません。そのような世の人々のために、その人に代わって祈るのです。
今朝、柏市の中で主の日の礼拝に集っている人は、一体何人いるでしょうか。2000人はいないでしょう。50万近い人の中で、ほんのわずかな者だけが神様の御前に集って礼拝している。それは、この柏市に住むすべての人のために、その人たちに代わって私たちが礼拝しているということなのです。その意味では、このように主の日に礼拝をささげるということ自体が、実に主イエスの十字架を背負ってなされる営みなのです。しかしそれは、誰にも感謝されることはないでしょう。でも、それでよいのです。なぜなら、主イエスはお喜びになられるからです。そこに、私たちの喜びもあるからです。私たちはただ主イエスに喜ばれること、それを何よりも喜びとするものとされた者だからです。ただ主イエスに喜ばれる歩みを、神様の御前になしていきたいと思います。お祈りをいたします。
【祈り】主イエス・キリストの父なる神さま、あなたの貴き御名を心から讃美いたします。今日も敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。神さま、御子イエス・キリストは、ヴィア・ドロローサ、悲しみの道を歩まれました。ローマの兵士たちによる辱めと侮辱を受けられた主イエスは、ひと言の反論も報復の行為もすることなく、ゴルゴタをめざして十字架を背負って歩かれました。それはただひとえに私たちの身代わりとなって、罪の裁きである十字架の死を受けられるためでした。私たちを愛するがゆえに、主イエスは苦難と十字架の道を歩まれたのです。どうか、私たち信じる者たちも愛するということの深い意味を知ることができるよう、導いていてください。そして私たちの身代わりとなって十字架を負ってくださった主イエスに、心からの感謝と讃美を捧げさせてください。今週の後半は冬の厳しい寒さがやって来るようです。どうか、教会につながる兄弟姉妹の心身の健康をお支えください。この拙き切なるお祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 創世記3章1~13節
説 教 「蛇の誘惑」 高橋加代子
午前10時30分 司式 山根和子長老
聖 書
(旧約) 詩編22編7~22節
(新約) マルコによる福音書15章21~32節
説 教 「辱められ、罵られても」 藤田浩喜牧師
マルコによる福音書15章1~15節 2026年1月11日(日)主日礼拝説教
牧師 藤田浩喜
今朝与えられている御言葉には、総督ピラトによって主イエスが十字架に架けられることが決められた場面が記されています。ここには、主イエスの周りを取り囲むように、四つのグループの人々が出てきます。第一は、総督ピラトです。彼は、ローマから遣わされているユダヤの総督でした。彼が主イエスを十字架につけることを決めたのです。第二は、祭司長・長老・律法学者といった、最高法院を構成していたユダヤの指導者たちです。彼らが主イエスを死刑にすべきだと決めて、総督ピラトの元に主イエスを連れて来たのです。第三に、群衆です。「十字架につけろ」と叫んで、ピラトに主イエスを十字架につける決断を迫ったのでした。第四に、バラバです。彼は暴動を起こして人殺しをし、投獄されていた人です。彼は主イエスが十字架に架けられることになって、本来自分が十字架に架けられることになっていたのに、釈放されることになりました。まことにラッキーな人でした。
主イエスの十字架への歩みを読み進める中で思わされることは、主イエスの十字架は、誰か一人の責任、誰か一人の罪によってもたらされたものではないということです。今日の所で言うならば、祭司長・長老・律法学者たちの訴えがなければ、主イエスは十字架に架けられることはなかったでしょう。しかし、彼らだけで主イエスを十字架に架けることができたかというと、そうではない。だから総督ピラトの所に連れて来たのでしょう。当時のユダヤの指導者たちには、死刑を執行することはできなかったからです。だったら総督ピラトが悪いのか。確かに、使徒信条やニカイア信条には「ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ」とあります。彼ほど、世界中で自分の名前が唱えられている人はいないでしょう。しかも良い意味ではないのです。主イエスを十字架に架けた人として唱えられ、覚えられているのです。
しかし、今日の所を読んでみますと、ピラトは主イエスを何とか十字架に架けないで済むように動いている。しかし、それを阻止したのは、群衆の「十字架につけろ」という叫びでした。もちろん、祭司長たちが主イエスを亡き者にしようとしなければ、主イエスを捕らえることがなければ、こうはならなかった。また、ピラトが「イエスを十字架には架けない」と宣言すれば、こうはならなかった。私はこの場面を思いながら、祭司長・長老・律法学者たちと総督ピラトそして群衆が、それぞれ役割を果たしながら、それぞれの人々の中に渦巻く罪が一つになって、牙をむいて主イエスに襲いかかっている、そんなイメージを持ちました。あの人がこう言ったから、この人がこうしたから、そんな個人の力や業によるのではなくて、人間の奥底にある罪が連動して一つになり、黒い怪物のようになって主イエスに襲いかかっている、そんなイメージです。その罪には、積極的なものもあれば、消極的なものもあります。
ここで消極的なのはポンテオ・ピラトです。彼は、何とか主イエスを助けようとしたのです。しかし結局、彼はそうしなかった。彼は知っていたのです。主イエスが十字架に架けられねばならないような悪いことは何もしていないということを。主イエスが祭司長たちに連れて来られたのは、「ねたみ」のためであることも知っていたのです。しかし、彼は主イエスを無罪にしなかった。主イエスを無罪放免にすれば、群衆が騒ぎ出し、暴動になりかねない。そんなことになれば、総督としての自分の立場が悪くなる。総督としての能力をローマ皇帝から疑われかねない。ピラトはローマ帝国という巨大国家の権力を代表していました。しかし彼はその力を、自分を守るために用いたのです。そして、主イエスを十字架につけることにしたのです。
まず、総督ピラトは主イエスにこう問いました。2節「お前がユダヤ人の王なのか。」多分祭司長たちが、そのような者として主イエスを訴えたからでしょう。
この時の主イエスの答えは、少々分かりにくい、謎に満ちたものでした。「それは、あなたが言っていることです」と主イエスは答えました。原文を直訳すると、「あなたが言った」です。これでは、ピラトの問いに対して肯定しているのか否定しているのか、よく分かりません。口語訳では意訳して「その通りである。」と訳しておりました。そのように理解する仕方もあります。しかし、これは意訳し過ぎではないかと思います。ここで主イエスは、ピラトに対して肯定も否定もしていない。そもそも、ピラトの言う「ユダヤ人の王」とは政治的な王であって、それしか彼は知りませんし、関心がないのです。その政治的な意味では、主イエスはユダヤ人の王ではありません。しかし神の子という意味なら、まことに主イエスはユダヤ人の王なのです。ですから答えようがない。そういう意味で、ユダヤ人の王というのはあなたが言っていることだ、ということでもあったでしょう。
さらに言えば、あなたはそう言っているが、わたしがユダヤ人の王であるかどうか、本当はどう思っているのだ。そのようにも読めるでしょう。しかし、ピラトにはそのような主イエスの思いは全く通じなかったでしょう。ですから、何も答えない主イエスを、ピラトはただ不思議に思うだけだったのです。
次に、祭司長・長老・律法学者たちです。彼らは、十字架に架けるために、主イエスを総督ピラトの元に連れて来ました。ローマの支配の下にあった彼らには、主イエスを殺すことができなかったからです。そして、こうも考えられます。ユダヤ教における処刑の仕方は、石打ちです。これも残酷なものですが、申命記21章23節に「木にかけられた死体は、神に呪われたもの」という言葉があります。彼らは、何としても主イエスを十字架に架け、主イエスを神に呪われた者として殺す、そういう意図があったのではないかと思うのです。そうすれば、もう誰も主イエスにはついて行かないだろう。そう願ったのでしょう。そして、そのためには罪状さえも変えて、ピラトの元に送ったのです。目的のためには手段を選ばない。彼らが大切にしていた十戒の第九戒に「偽証してはならない」とありますが、これを平気で破るのです。
しかし、主イエスは反論もせず、何も答えず、黙ったままでした。主イエスはこの時、御自身がマタイによる福音書10章28節で言われた「体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい」との御言葉を思っておられたのではないかと思います。主イエスは何も恐れていないのです。
そして、群衆です。彼らは数日前、主イエスがエルサレムに入られる時、「ホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。我らの父ダビデの来たるべき国に、祝福があるように。いと高きところにホサナ」と叫んで、主イエスを迎えたのです。神殿において主イエスが話されるのも喜んで聞いていたのです。しかしこの時、彼らは祭司長たちに扇動されてしまいます。総督ピラトが、「釈放して欲しいのはイエスか、人殺しのバラバか」と問うた時、「バラバを釈放せよ」と叫び、「イエスをどうして欲しいのか」と問うた時、「十字架につけろ。」と叫んだのです。私はこの時の群衆の叫びは、声を揃えて何度も何度も叫んだのではないかと思います。12~14節「そこで、ピラトは改めて、『それでは、ユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者は、どうしてほしいのか』と言った。群衆はまた叫んだ。『十字架につけろ。』ピラトは言った。『いったいどんな悪事を働いたというのか。』群衆はますます激しく、『十字架につけろ』と叫び立てた。」それは、もう誰も止められないような熱に浮かされた叫びだったのでしょう。
群衆は扇動されただけだ。そうかもしれません。一人一人はそれほど自覚のないままに、祭司長たちに扇動されて叫んでいただけなのかもしれません。しかし私には、人間の罪が一つに合わされ、強大な力となり、ローマの総督ピラトでさえも言うことを聞かねばならないほどのものとなった。私はこの時一人一人の罪が合体し、黒い怪物のようなものになって、主イエスに襲いかかっているように思えてならないのです。先の大戦へと突入していった際の日本国民の熱狂とも重なります。先の大戦が始まるとき、日本国民は熱狂し、提灯行列をして喜んだのです。やがて自分の夫や子どもたちが戦地に行くというのにです。この時「十字架につけろ」と叫んだ群衆は、皆で一つの言葉を叫び、高揚した一体感に満ちていたのではないでしょうか。彼らもまた、主イエスを十字架につけるために、決定的な役割を果たしたのです。
今、総督ピラト、祭司長たち、群衆といった人たちが、それぞれ主イエスを十字架に架けるために役割を果たしていったことを見ました。どれが欠けても、主イエスは十字架に架けられることはなかったのです。そして、今朝私たちが確認したいことは、この人々は、今朝ここに集っている私たちが主イエスと出会う前の姿、私たちの心の奥底に今もうごめいている罪の姿だということなのです。誰も、私はピラトではない、祭司長たちではない、この時の群衆ではないとは言えないでしょう。自分を守るためならば、平気で嘘もつくし、誰かのせいにもする。無意識にそうしている。しかし、そのような一人一人の罪が一つに合わさって、巨大な罪の台風のようなものが渦を巻いてすべてを巻き込んでいくその中で、主イエスは誰も恐れず、何も恐れず、沈黙しておられた。それはこの一切の罪を担い、これに勝利するためだったのです。
そして、最後にバラバ。彼は人殺しでした。彼こそ暴動を起こした人であり、十字架に架けられるはずの人でした。ところが、主イエスが十字架に架けられることになって、彼は助かってしまうのです。彼は、何もしていません。自分が裁かれ十字架に架けられることから救われるために、彼は何もしていない。ただ、主イエスが十字架に架けられることになっただけです。このバラバこそ、主イエスの十字架によって救われることになった私たちの姿なのです。私たちはバラバなのです。まことに不思議です。
人間の罪は一つの塊(かたまり)となり、神様に敵対し、主イエスに敵対し、遂に主イエスを十字架に架けて殺すことになった。しかし、そのことによって、人殺しのバラバが救われるのです。これが神様の御業というものです。人間の最も罪深い業をも用いて、その救いの御業を貫徹されるのです。私たちは、このまことに不思議な神様の御業の中で選ばれ、主イエスと出会い、主イエスを信じて従う者とされました。こうして、主イエスの前にひざまずく者とされました。罪を赦され、神の子とされ、新しい命に生きる者とされました。まことに不思議なことであり、まことにありがたいことではないでしょうか。
今、主イエスを「十字架につけろ」と叫ぶ罪から解き放たれ、主イエスを「我が主、わが神」と礼拝し、ほめたたえる者とされたことを、心から感謝したいと思います。そして、そのような御業をなさった神の御名を共々にほめたたえて、新しい一週間を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。
【祈り】主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を心から褒め称えます。今日も敬愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝することができましたことを、感謝いたします。総督ピラトのもとでなされた裁判の場面を学びました。主イエスは無実であられましたが、ピラトによって死刑に判決を受けました。それはピラトだけがなしたものではなく、ユダヤの指導者たち、群衆たちの罪が一つの塊となって、主イエスに襲い襲いかかった結果でした。しかしあなたは、そのような人間の罪と悪が合わさり極まった主イエスの十字架によって、私たちの罪を贖い、赦してくださいました。私たちはあなたの御業に驚くことしかできません。どうぞ、十字架の死を免れたバラバの中に私たち自身の姿を見出し、あなたの御業を心から褒め称える者としてください。冬の寒さが厳しさを増しています。どうか、教会につながる兄弟姉妹一人一人の心身の健康を支えていてください。このひと言の切なるお祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 ルカによる福音書4章1~13節
説 教 「荒れ野の誘惑」 山﨑和子長老
午前10時30分 司式 山﨑和子長老
聖 書
(旧約)エレミヤ書33章1~11節
(新約) マルコによる福音書15章16~21節
説 教 「悲しみの道」 藤田浩喜牧師
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 ルカによる福音書3章21~22節
説 教 「主イエスの洗礼」 藤田浩喜牧師
午前10時30分 司式 三宅恵子長老
聖 書
(旧約) エレミヤ書33章12~16節
(新約) マルコによる福音書15章1~20節
説 教 「唯一の真実の王」 藤田浩喜牧師
ローマの信徒への手紙12章1~8節 2026年1月4日(日)主日礼拝説教
牧師 藤田浩喜
新年最初の主日を迎えました。この日、共に礼拝をお捧げできますことを嬉しく思います。教会の暦においては、一年はアドベントから始まります。ですから、私たちはすでに昨年の11月30日から新しい年のサイクルをスタートしているとも言えます。しかし、この国に住んでいますとやはり生活感覚としての年の初めは、どうしてもお正月になりますでしょう。
アドベントにせよお正月にせよ、いずれにしても年の初めの区切りがあるということはありがたいことです。それは一年を振り返り、新しい生活へと歩み出す機会となるからです。そうでなければ何の反省も進歩もなく、旧態依然とした生活を漫然と続けてしまうかもしれませんから。
今日の新約聖書の箇所として読まれましたのは、ローマの信徒への手紙12章でした。この手紙においてはここから新しい区分に入ります。この区分においてはキリスト者の生活について語られています。キリストによって与えられる「新しい生活」について語られていると言ってもよいでしょう。しかし、直接的に「新しい生活」という言葉は出てきません。書かれていたのは「心を新たにして」という言葉でした。「あなたがたはこの世に倣ってはなりません。むしろ、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい」(2節)。
「心を新たにして」。原文では「心の一新」という意味合いの言葉です。心を置き去りにして、生活だけを変えることはできません。まず必要なのは心の一新です。心を新たにすることなくして生活が新たになることはありません。
しかし、「心の一新」と言いましても、いろいろな一新の仕方があるように思います。実際、新年には何らかの決心をし、心新たに何かに取り組もうとする人は少なくないのでしょう。では、聖書が語る「心の一新」とはどのような意味合いなのでしょうか。
「心を新たにして」の前にパウロが言っていたのは、こういうことでした。「あなたがたはこの世に倣ってはなりません」。そのように語られているのは、一方において「この世に倣う」という生き方があるからです。また、それを生み出す心の方向性があるからです。そして、それは教会の中にも入ってきており、私たちが知らず知らずのうちに、そのような心をもって、そのような生活をしているということがあり得るからです。
それは教会がこの世に存在し、信仰者の人生もまたこの世において営まれている限り、避け得ないことなのでしょう。だからこそ、「心の一新」が必要なのです。心の方向転換が必要なのです。そして、この世に倣わない生き方への転換が必要なのです。
しかし、「この世に倣わない」とは何を意味するのでしょうか。これもまた人によって思い描くことは様々なのでしょう。
あるキリスト者は「この世に倣わない」ということで真っ先に「禁酒禁煙」を考えるかもしれません。別な人は「この世に倣わない」ということで、弱い立場にある人に対する優しさや思いやりを持つということを考えるかもしれません。また他の人は「この世に倣わない」ということで、右傾化する社会の動きに対して抵抗することを考えるかもしれません。教会やキリスト者に対して二人の人が「これではこの世と同じではないか」と言ったとしても、その二人が必ずしも同じことを考えているとは限りません。
では、パウロ自身はどのような意味において、「この世に倣ってはなりません」と言っているのでしょうか。「この世に倣ってはなりません」とは否定的・消極的な表現です。彼はすぐにこれを、肯定的・積極的な表現で言い換えます。《こうしてはならない》というだけでなく、むしろ積極的に《こうあって欲しい》という思いがあるのです。彼は言います。「むしろ、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい」。この世に倣わないとは、こういうことです。
そこには、「何が神の御心であるか」と書かれています。当然のことながら、この世は「何が神の御心であるか」ということで動いているわけではありません。この世を動かしているのは、「何がわたしの望んでいることか」「何が私たちの望んでいることか」という人間の欲求と願望です。同様に、この世は「何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるか」ということで、動いているわけではありません。この世を動かしているのは、「何がわたしたちにとって善いことで、わたしたちに喜びと満足を与えるのか」という人間の判断です。国家としてならば、「何が国益となるのか」という判断になるのでしょう。
そのようなこの世の姿といつのまにか同じ姿になってしまっていることは、私たちにも確かにあります。この世と同じように、いつでも関心は「わたし」あるいは「わたしたち」のことでしかないことが起こります。そう、必ずしも「わたし」ではない。「わたしたち」を強調すれば、エゴイスティックに見えないこともあります。しかし、関心はあくまでも人間の側のことなのでしょう。自分たちの望みが実現し、自分たちが喜び、自分たちが満足を得ることであり、望みが実現しなければ失望し、満足を得られなければ不平を言い、互いに相争うことにもなるのです。
そのように、知らず知らずのうちにこの世に倣い、この世と同じ姿になっていることが、私たちにも確かにあるのです。だからこそ、「心の一新」について語られているのです。それが必要なのです。「わたし」「わたしたち」と、こちら側のことにばかり向いているこの心が、ぐいっと方向転換をして、神に向けられることが必要なのです。「何が神の御心であるのか」「何が善いことで、神に喜ばれることなのか」に、心が向けられることが必要なのです。それこそが、「心を新たにする」ことなのです。
心を新たにするところから、新しい祈りが生まれてきます。ただ自分たちの望みの実現を求める祈りではなく、自分たちの満足を求める祈りでもなく、「御心を教えてください」という祈りが生まれてくるのです。「何が善いことで、何があなたに喜ばれることなのかを教えてください」という祈りが、私たちの内に生まれてくるのです。
そして、御心に従って生きようと思うなら、自分が変えられなくてはならないこともまた分かるのです。だからパウロは、「自分を変えていただきなさい」と言うのです。これは「変えられ続けなさい」という表現です。「むしろ、心を新たにして、自分を変えていただき、変えられ続けていきなさい!」。そこにこそ、本当の意味での新しい生活があるのです。
しかし、今日は与えられた聖書箇所から、なお一つのことを心に留めたいと思います。パウロは続けてこう言っています。「わたしに与えられた恵みによって、あなたがた一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません」(3節)。
このあと、信仰生活に関する具体的な勧めが15章まで続くことになるのですが、その最初に語られていることがこれです。心を新たにして自分を変えていただき、神の御心をわきまえて生きようとする人が、最初に聞かなくてはならない言葉がこれなのです。「自分を過大に評価してはなりません」。むしろ「慎み深く評価すべきです」と言うのです。
この言葉で何を言わんとしているのか。続く4節以下から明らかです。要するに、自分が体の一部に過ぎないことをわきまえなさい、ということです。5節に「わたしたちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形づくっており、各自は互いに部分なのです」と書かれているとおりです。私たちは神の御心を行う大きな体の一部なのです。部分ならば部分としての働きで十分なのです。全てをなし得なくてもよいのです。自分を体の全てであるかのように、評価してはならないのです。
そうであるなら、他の人ができることを自分ができないとしても、それでよいのです。部分なのですから。他の人を羨む必要も、自らを卑下する必要もないのです。自分になし得ることを他の人が同じようにできないとしても、批判する必要はないのです。自分は自分の与えられた務めに専念し、他の人は他の人のなし得るところを行ったらよいのです。
6節で聖書は、「わたしたちは、与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから…」と言います。この世に倣って生きようとするならば、自分の願望の実現のために自分を用いて生きようとするならば、この能力が足りない、あのこともできない、とつぶやきながら、他人を羨み、自分を卑下して生きることにもなるのでしょう。しかし、心を一新して神の御心のために生きようとするならば、そのために必要な全てはすでに賜物として与えられているのです。神の御心を求め、自分を献げて生きるならば、与えられている賜物が何であるかも見えてくる。また、自分が体のどの部分なのか、専念すべきことは何であるのかも見えてくるのです。
新しい年を迎えました。このような区切りが与えられていることは幸いなことです。これまでこの世に倣い、この世と同じものを追い求め、この世によってこの世と同じ姿にされていたならば、この年の区切りは私たちの信仰生活を振り返り、心を一新する機会です。心を置き去りにして、生活だけを変えることはできません。心を新たにして自分を変えていただきましょう。変えられ続けることを求めましょう。そして、キリストによって一つの体とされている私たちとして、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるかに思いを向けて、共に仕えてまいりましょう。お祈りをいたします。
【祈り】主イエス・キリストの父なる神様、あなたの貴い御名を心から讃美いたします。2026年の最初の礼拝を敬愛する兄弟姉妹と共に守ることができましたことを、感謝いたします。パウロの手紙を通して、心を新たにすることを教えられました。私たちの歩みはともするとこの世に倣い、私たちの願いや私たちの目的を追い求めてしまいます。あなたは心を新たにし、あなたが願っておられること、あなたが喜ばれることを求めるよう、私たちを促しておられます。どうか、この世に倣うのではなく、あなたに心を向けて、あなたの御心を尋ね求めることができますよう、私たちを励ましてください。日々冬の寒さが厳しくなっています。どうか、教会につながる兄弟姉妹一人一人の心身の健康をお支えください。
このひと言の切なるお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
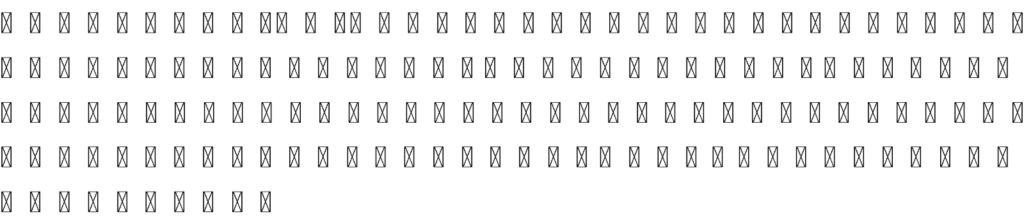
午前9時15分-10時 礼拝と分級
聖 書 ルカによる福音書2章41~52節
説 教 「神殿での少年イエス」 山根和子長老
午前10時30分 司式 藤田浩喜牧師 (聖餐式を執行します)
聖 書
(旧約) エレミヤ書31章31~34節
(新約) ローマの信徒への手紙12章1~8節
説 教 「心を新たに」 藤田浩喜牧師